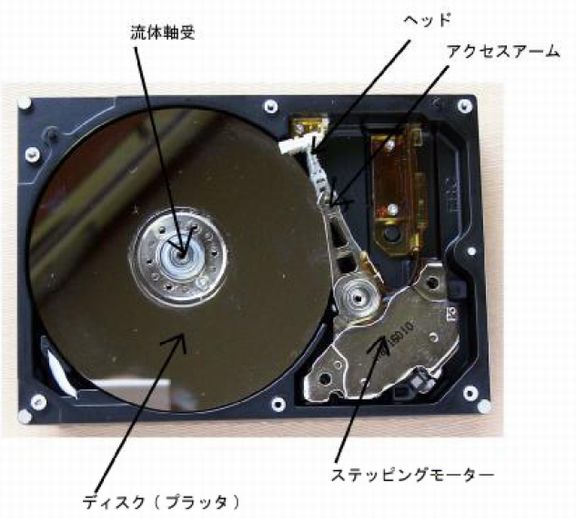
写真1 内部構造
講師 森田矩夫 さん
[概要]
私のパソコンから取り出した故障した Hard Disk Drive を分解して内部構造を調査した。
その写真とHDD に関する最新技術について解説する。
調査対象:IBM IC35L060AVER07-0 61.5GB 3.5inch 7,200rpm 2001-10製造
[写真]
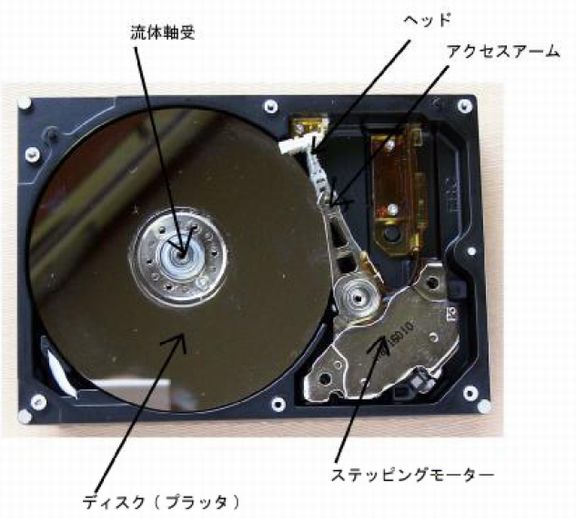
写真1 内部構造

写真2 裏面形状
{余談} HDD は 1956年にIBM が発明。これは 24吋ディスク50枚から構成されていたが、記憶容量はたったの 4.4MB しかなかった3)。
[基本構造]
1.記録部
記録ディスク(プラッタ) 3.5、2.5、1.8、1.0 吋 40GB/3.5"/枚 4枚構成
2.読み書き部
ヘッド GMR 再生ヘッド スライダ(ca.1x1.2x0.3mm)の小型化
アクセスアーム オートリトラクト機能
3.駆動部
スピンドルモーター 5400、7200、10000、15000 rpm
流体軸受 流体動圧軸受
4.コントロール基板
[記録ディスク構造の例1)]
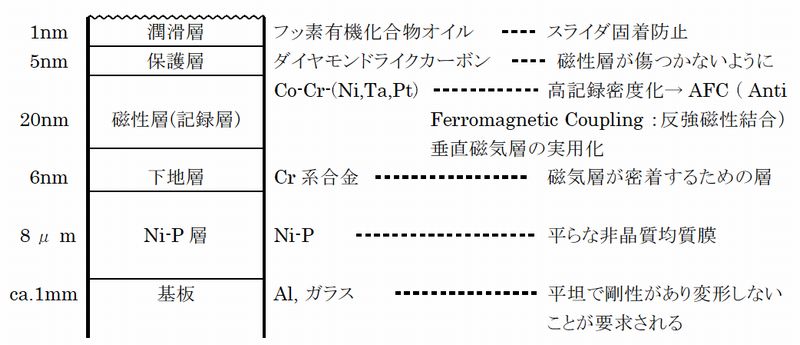
[ヘッド技術]
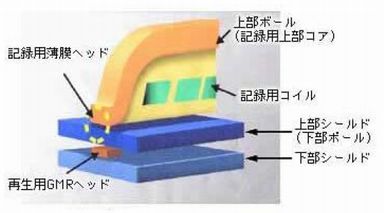 |
| 図1 ヘッド構造図2) |
[ヘッドの飛行]
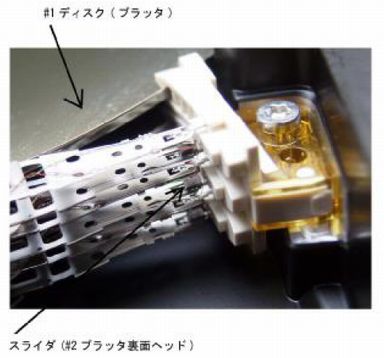 |
| 写真3 スライダ(四角の部分)とシッピングゾーン |
[Hard Disk Drive メーカー]
○ Maxtor
○ Seagate
○ Hitachi Grobal Strage Tecghnologies(日立+IBM )
○ Western Digital
○ 富士通 東芝 Sumsung Electronics
[文 献]
1)押木満雅:「ストレージングデバイスの現状と今後の動向」 20003/09/23
2)電波新聞別冊 2003/01/09
3)伊勢雅英:「伊勢雅英の最新 HDD テクノロジ探検隊[前編]」 Enterprise watch 2005/04
4)楠清尚:「HDD 用動圧ベアファイトユニット」 NTN TECHNICAL REVIEW No.71 (2003)